「仕切らない」「口を出さない」:できる課長の「やらない」メソッドとは?
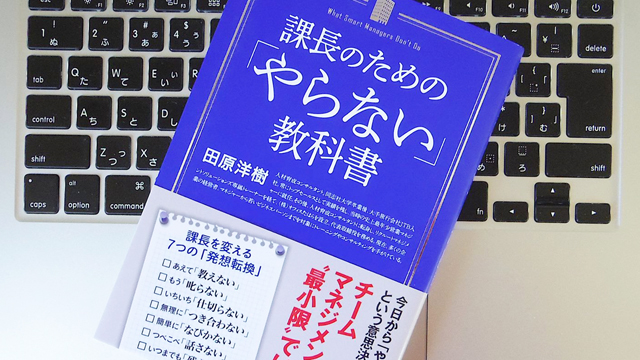
※出典:Lifehacker
個人プレーにおいては優秀な実績を残してきた人が、課長職などの立場に立った途端に戸惑い、成果を出せなくなる。そんなことは、よくあるものです。『課長のための「やらない」教科書』(田原洋樹著、三笠書房)の著者もそうした苦しい過去を通ってきたそうですが、その結果、ひとつの確信に到達したのだといいます。
それは、厳しいなかでもいきいきと「やりたいこと」を実践している課長こそが、結果的に成功しているということ。歯を食いしばって「やらなければならないこと」と向き合うのではなく、縦横無尽に、ときには自分勝手とさえ映るような行動を続けながらも、部下から慕われ、上司とも良好な関係を保ち、成果も上げ続けられる課長が存在しているというのです。
そんな課長になるには、「やらないことを決める」ということから始める必要があります。やるべきこと、つまり「優先順位」を決めるのではなく、やらないこと、いわゆる「劣後順位」を決めていくことが必要です。(「はじめに」より)
そこで本書では、「教えない」「叱らない」「仕切らない」「つき合わない」「なびかない」「話さない」「残らない」というテーマごとに、「やらないこと」を整理しているわけです。きょうは、第3章「いちいち『仕切らない』 ──部下に「主体性」を発揮させるコツ」をクローズアップしてみたいと思います。
なぜ、あれこれ口を出してしまうのか?
課長は、チームの仕事を直接マネジメントする立場ですが、だからといってチームメンバーの業務を仕切る必要はないと著者は断言しています。課長は一歩引いて、後方で見守るほうがうまくいくケースは多いということ。ただし、頭ではわかっていても、つい仕切ってしまう課長が多いのも事実。そこで著者はここで、「部下に仕事を任せることができず、自分で仕切ってしまう人」の考え方を整理しています。
1. 元来「仕切りベタ」の自分に、劣等感を感じている
「仕切りベタ」を自覚しているからこそ、あえてそれを包み隠すかのごとく懸命に仕切るタイプ。しかし、苦手意識を持ちながら無理に仕切ると、かえって空回りしてしまうわけです。そこで、「自分は仕切れないから、誰かやってくれ」と開きなおることが必要だといいます。劣等感は自分自身が抱く感情に過ぎず、周囲はなんとも思っていないものだから。
2. 「プレイヤー」であることを正当化している
プレイヤーから抜け出せない責任を、人材不足という環境要因に押しつけてしまう課長。「本来ならマネジメントに特化したいが、人手が足りないから仕方なくプレイヤーを続けている、だから現場に介入せざるを得ない」という人は、プレイヤー時代の成功体験から離れられないだけ。プレイヤーとして活動し続けることの正当性を見出したいがために、そのような言い訳をしているにすぎないというのです。
課長の多くは、プレイヤー時代に華々しい活躍をしてきた人たち。その実績や思い出が耀ければ輝かしいほど、残像がいつまでも記憶に残り、かえってマネジメントに特化する意欲を阻害してしまっているのだといいます。
3.「征服欲」を得たいと思っている
「仕切る」という行為が心地よいため、支配欲の強いタイプはこの傾向が強いのだそうです。また、プライドが高く、自信家の人にも「仕切る課長」が多く見受けられるのだとか。ただし、ここで間違うべきでないのは、その心地よい状況を、部下たちも心地よく感じているわけではないということ。
「仕切られた方が楽」と感じる部下がいる一方、「仕切る」のが心地よいタイプの部下もいるわけです。当然ながらそうしたタイプは、「仕切られる」ことに強い抵抗感を持っているでしょう。なお著者は、もし自分のチームに10名のメンバーがいたとしたら、自分と同じタイプの人は2人以上いるものだと解説しています。
4. 部下の能力を過小評価している
部下のことを心の底で「能力のない者」と過小評価しているこの手のタイプは、かなり多く存在するのだといいます。
こうした思考に陥るのは、仕事の能力というものが、職務に携わった時間に比例して右肩上がりに伸びていくと考えているから。しかし、いうまでもなくこれは間違った考えです。能力の伸び方は時間だけではなく、仕事の質や本人のポテンシャル(潜在能力)でも大きく変わってくるものなのだから。
「若いから」「経験がないから」と必要以上に過小評価するのではなく、個々人が持つ能力を適正に見極める力こそが、現場にもっとも近い管理職である課長には求められるということです。
5.「仕切る」以外のコミュニケーション法を知らない
部下との関わり方、つき合い方を、「仕切る」というスタイル以外に知らないタイプの課長がいるそうです。こういう人はマネジメントスタイルにおいて、自分の上司だった人から強く影響を受けているもの。つまり自分のなかにある「課長像」が他に見当たらないというのです。
このタイプの大きな要因は、後方から「見守る」、「縦」のラインではなく「横」のラインで「一緒に考える」というスタイルでマネジメントする上司に出会ってこなかったこと。だからといって、マネジメントスタイルを変えようとしないのは怠慢だと著者。なぜなら、変えようと思えば、それはすぐに変えられるから。マネジメントに対する考え方、マネジメントのスタイルを変える──その勇気を持つことこそが大切だというのです。
これらを見ればわかるとおり、部下が未熟なのではなく、課長の考え方に問題が隠れていることも決して少なくないもの。だからこそ、「仕切る」という行為が、部下の貴重な成長チャンスの芽を摘み取ってしまっていることに、課長自身が気づく必要があると著者は主張します。(90ページより)
できる課長の「仕事の任せ方」
では、仕事をどう任せればいいのでしょうか? この問いに対する返答として、著者は「仕事の任せ方」(権限移譲の方法)を3つ紹介しています。
1.「なぜ、君にやらせるのか」──その「想い」を伝える
「特異な領域のさらなるスキルアップを図ることで、この分野の第一人者となってほしい」など、仕事を任せることについての想いをメンバーに伝えることは課長の責務。なおその際、しっかりとしたロジックを示してあげると効果的だといいます。
2.「仕事の進め方・やり方」は本人に任せる
権限を委譲する際、仕事の進め方・やり方をこと細かに指示したのでは、仕事を任せたことにはなりません。もちろん一定の結果は求めるものの、そこに至るプロセスについては、過度な指導をせず、ある程度自由に取り組ませることが必要だということ。そうすることでメンバーは、「やらされ感」を感じることなく、自由にプロセスを設計できるわけです。
従来の進め方・やり方があるのであれば、それはあくまで参考程度に開示する。しかしそこに固執せず、部下に自分なりの考え方や発想を投入してもらいたいという意思表示をする。それが課長に求められるべきこと。権限を委譲するには、プロセスも含めていったんゼロベースにするという勇気が不可欠だという考え方です。
3. 成功時はメンバーを称え、失敗時は自分を責める
「手柄は部下に、失敗は自分の責任に」が理想だとはいうものの、現場では正反対のことが起こりがち。しかしチームのメンバーが成功したとき、課長が任命権者である自分の手柄を上層部にアピールし、失敗したらメンバーの能力不足を攻めるというようなスタンスでは課長失格。
「上司は、手柄は部下に渡し、失敗は自分で引き受ける」という姿勢を貫くことが、結果的には周囲のメンバーに「課長の覚悟」を伝えることになり、チームを一丸とするということです。(112ページより)
いうまでもなく本書は、課長をターゲットにしたものです。しかし内容的には、人の上に立つポジションにいるすべての人に役立つはず。リーダーシップのあり方に頭を悩ませている方は、手に取ってみるといいかもしれません。
(印南敦史)
元記事を読む
関連記事
| 逃げる技術で仕事スムーズ |
| ワーク・ライフ・◯◯◯ |
| 効率アップ 高密度化仕事術とは |
- ブーストマガジンをフォローする
- ブーストマガジンをフォローするFollow @_BoostMagazine_










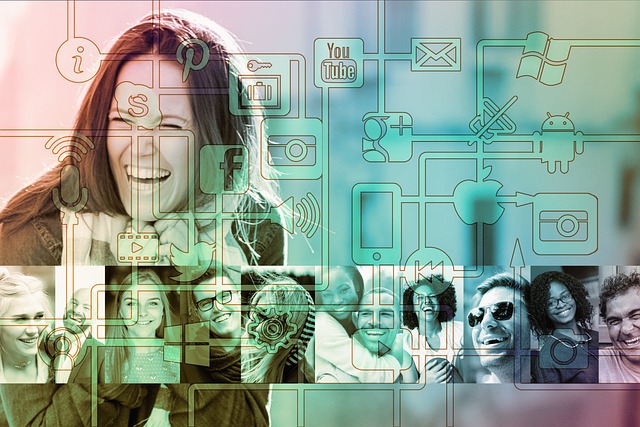

 【PR】PostPetの「モモちゃん」に会える!桜の季節の中目黒で笑顔になれるひ
【PR】PostPetの「モモちゃん」に会える!桜の季節の中目黒で笑顔になれるひ 「24時間可愛いなんて無理」本音から知る女性社員への接し方とは?
「24時間可愛いなんて無理」本音から知る女性社員への接し方とは? 我が子の姿を美しく残す!子供の撮影テクをプロに聞いてきた!
我が子の姿を美しく残す!子供の撮影テクをプロに聞いてきた! 雨・雪の日の愛犬との散歩も楽しいね
雨・雪の日の愛犬との散歩も楽しいね 赤い悪魔を追い詰めた西野JAPAN、足りないものとは
赤い悪魔を追い詰めた西野JAPAN、足りないものとは




 Faceboook
Faceboook Twitter
Twitter